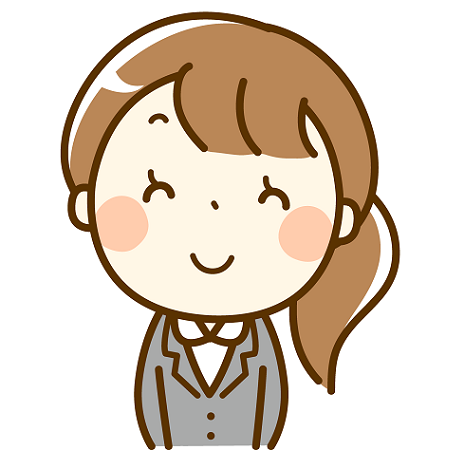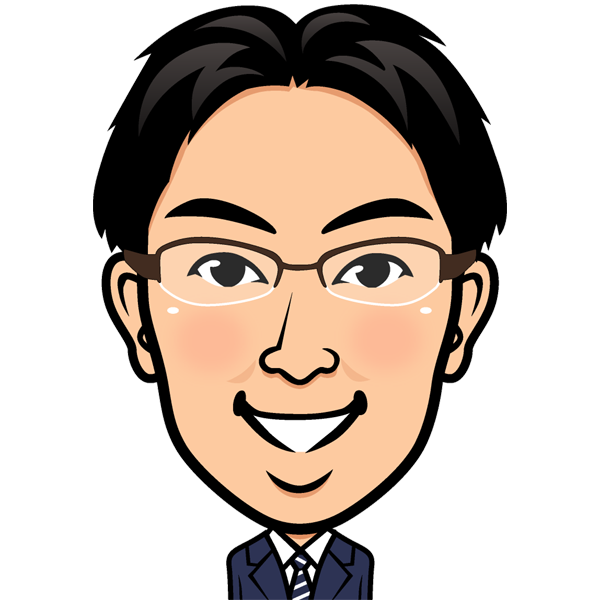

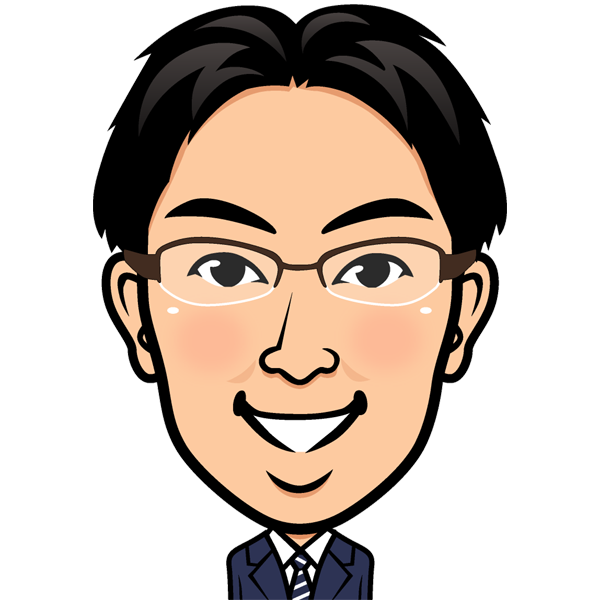
ということで本日は、特許出願・実用新案出願と意匠出願について、侵害という観点から解説していきましょう。
特許権に抵触しないかの検討の必要性


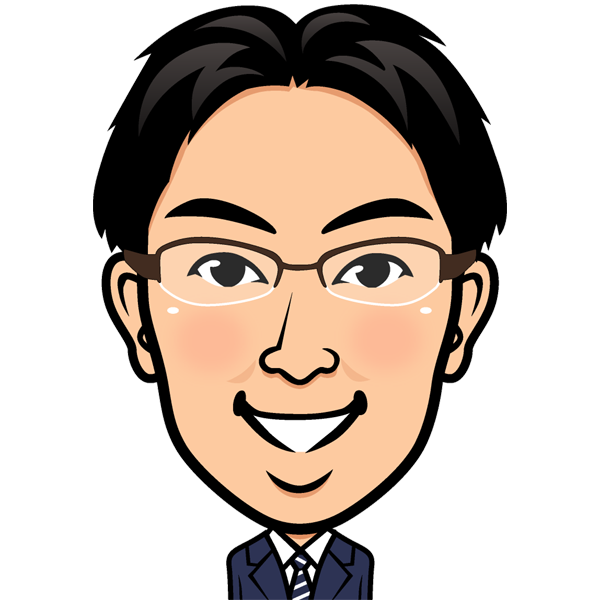
まず最初に、次の2点について解説していきましょう。
- 自社で新製品を企画する場合
- 他社の新製品が非常に売れゆきがよい場合、自社でも同じような製品を開発して販売しようとする場合
この場合、その他社がその新製品について特許権を取得しており、自社が製造・販売する製品がその特許権の技術的範囲に含まれる場合には、その特許権の直接侵害のうちの文言侵害(後述)となり、販売後の差し止めや損害賠償を請求されるリスクがあります。
よって、仮に他社の製品と同じ用途の製品を開発するとしても製品開発の当初から、当該他社の特許権について調査し、当該特許権の技術的範囲に含まれないようにすることが重要になります。
また、その際には、文言侵害だけでなく、均等侵害(後述)に該当しないようにしましょう。
また、直接侵害だけでなく間接侵害に該当しないようにしましょう。
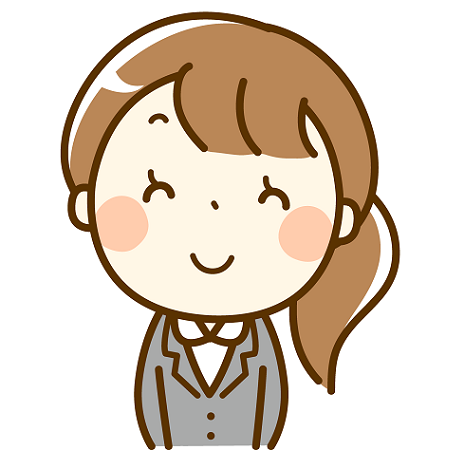
直接侵害とは


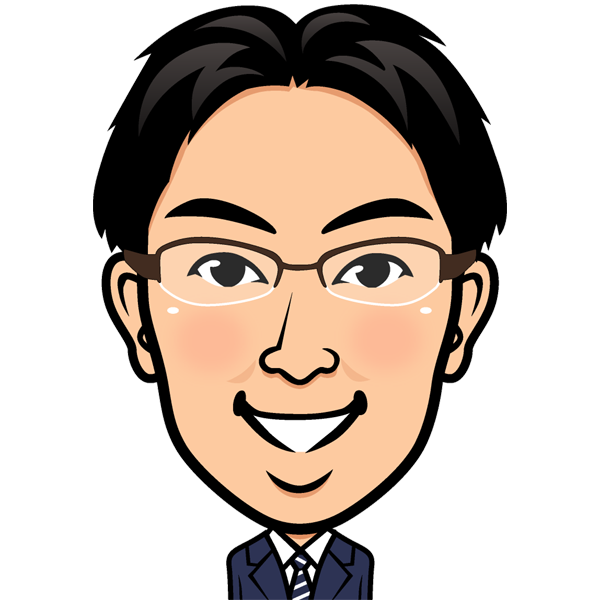
文言侵害とは
製品またはサービスが、特許権の特許請求の範囲のいずれかの請求項に記載された全ての構成要件を満たす場合に、文言侵害になります。
一方、1つでも構成要件を 満たさない場合には、文言侵害になりません。
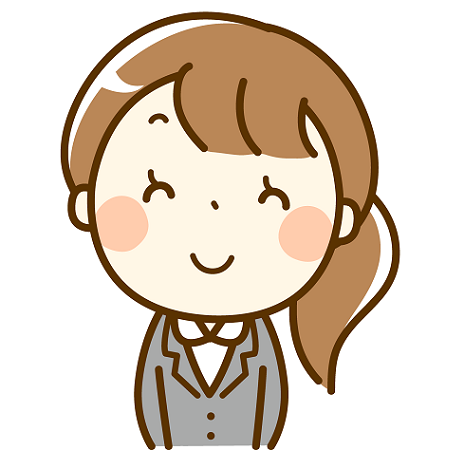
均等論(均等侵害)とは
均等論とは、請求項の文言どおり忠実に解釈すれば権利範囲に含まれないような物(方法)であったとしても、本質的に特許された発明を模倣していると考えられる場合には、均等物(均等方法)であるとして権利範囲に含める解釈をいい、このように特許発明の均等物に該当する場合、均等侵害といいます。
この均等論(均等侵害)は、たとえ請求項の文言の上では構成要件を充足していなくとも、実質的に特許発明を模倣している場合に、特許権の侵害でないとすれば、特許権者を実質的な模倣から保護することができなくなるので、上記のような場合を侵害とする判例上の理論です。

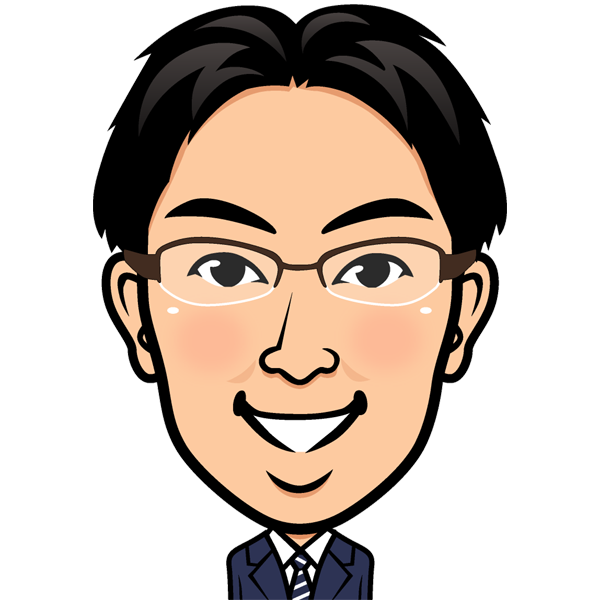
そのときの特許請求の範囲が以下の通りであったとします。
【請求項1】
黒色の芯材と、 前記芯材を取り囲み横断面において六角形の木材と、 を備えた鉛筆。
このとき、自社Y社が他社X社に無断で、横断面が六角形の赤鉛筆を販売したとします(ここでは仮に横断面が丸い赤鉛筆は世の中に知られているとします)。
他社Xが特許を取得した発明は、転がりにくくするために横断面を六角形にしたことが本質ですが、自社Yの赤鉛筆はその本質部分は模倣していますが、鉛筆の芯の色を変えているため、文言上権利範囲に入らないことになります。
そもそも上記の請求項の書き方がまずいのですが、このような場合であっても、芯材が黒色であることは特許発明の本質的な部分でなく、もともと赤鉛筆は世の中に知られていることから、横断面が六角形の芯材を黒色から赤色に容易に置き換えられ、置き換えても転がりにくいという同様の効果が得られることから、自社Yが赤鉛筆を販売する行為は、均等論により均等侵害となります。
均等侵害が成立するには、以下の5つの要件を満たす必要があります。
(第1要件)
特許発明の構成要件のうち対象製品(以下、イ号製品という)との 相違部分(上記の例では、芯材が黒色)が、特許発明の本質的部分ではないこと
(第2要件)
相違部分(上記の例では、芯材が黒色)をイ号製品に対応する部分 (上記の例では、芯材が赤色)に置き換えても、特許発明の目的(上記の例では、 転がりにくい)を達することができ、同一の作用効果(上記の例では、転がりに くい)を奏すること
(第3要件)
相違部分を置き換えること(上記の例では、芯材を黒色から赤色に 置き換えること)に、当業者が、イ号製品の製造の時点において(上記の例では、 自社Yの赤鉛筆の製造時の時点において)容易に想到することができたもので あること
(第4要件)
イ号製品が、特許発明の特許出願時における公知技術と同一又は当 業者がこれから出願時に容易に推考できたものではないこと (第5要件)イ号製品が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情もないこと
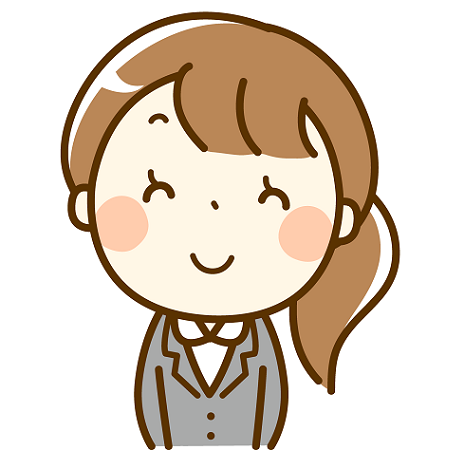
間接侵害とは


では、間接侵害というのはどのようなものでしょうか?
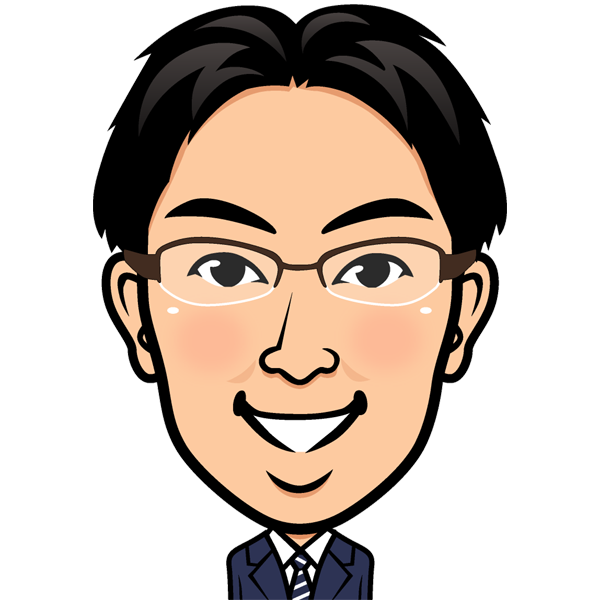
特許発明の直接侵害となるためには、製品または方法が、特許権の請求項に記載された全ての構成要件を満たす必要があります。
しかし、この原則を貫くと、妥当ではない結果が生じてしまいます。
例えば、特許侵害品を製造するための部品であって、他の用途のない部品の製造は、特許の直接侵害行為を誘発する危険の高い行為です。しかし、上の原則を貫くと侵害には問えず、差止請求などをすることができなくなってしまいます。
そこで特許法は、特許の直接の侵害行為には該当しないものの、侵害の蓋然性の高い一定の行為を禁止する趣旨で、間接侵害に関する規定を設けています(特許法 第101条)。
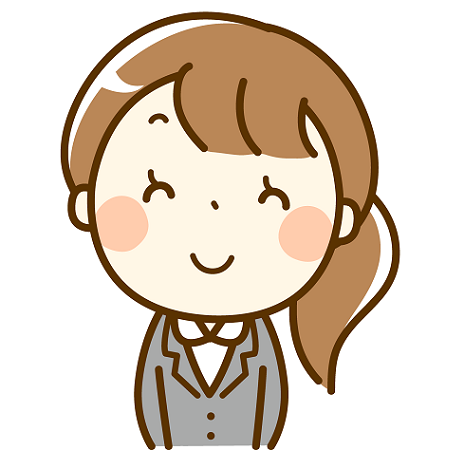
以下、間接侵害となる各行為につき、3つの類型に分けて説明します。
間接侵害の第1類型(特許法第101条1号、4号)
特許侵害を構成する物や方法に「のみ」用いられる物、つまり専用品の製造を特許権の間接侵害とみなす、という規定です。
ここでいう「のみ」とは、ある物が特許発明の直接の侵害品・侵害行為にかかる物の生産にのみ使用され、「実用的な他の用途がないこと」をいいます。
そしてこの「他 の用途」とは、抽象的・試験的な使用の可能性では足らず、社会通念から見て、経済的・ 商業的・実用的であると認められる用途であることを要する、と考えられています (東京高裁平成16年2月27日判決「リガンド分子事件」等)。
この「のみ」の立証責任は特許権者が負うものとされています。
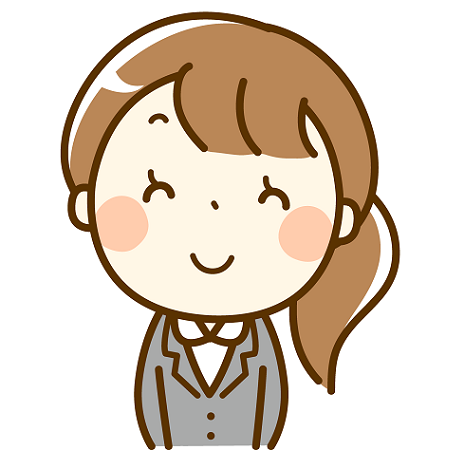
間接侵害の第2類型(特許法第101条2号、5号)
上述した第1類型の「のみ」品(専用品)の規定では、侵害行為・侵害製品に使用されることを知りつつ特許侵害品の重要部品等を供給する場合でも、専用品でなければ、間接侵害に該当しないこととなります。
しかしこの場合、侵害につながる蓋然性の高い予備的行為が差し止められないこととなり、特許権者の正当な利益が保護さ れない事態が生じ得ます。
そこで間接侵害の第2類型は、間接侵害に該当する物について「その発明による課題の解決に不可欠なもの」と限定した上で、行為者の主観的要件すなわち「その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知っていた」場合に、特許権の間接侵害にみなす、という規定です。
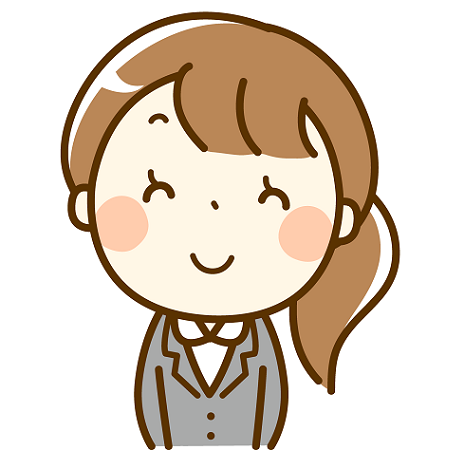
間接侵害の第3類型(特許法第101条3号、6号)
間接侵害の第3類型は、侵害品の個々の販売行為や流通を未然に防止するという目的から、譲渡等の前段階である「所持」行為を侵害とみなすことができるように設けられた規定です。
ただし、単なる所持では足りず、「譲渡等」又は「輸出」のために所持する行為が対象となります。