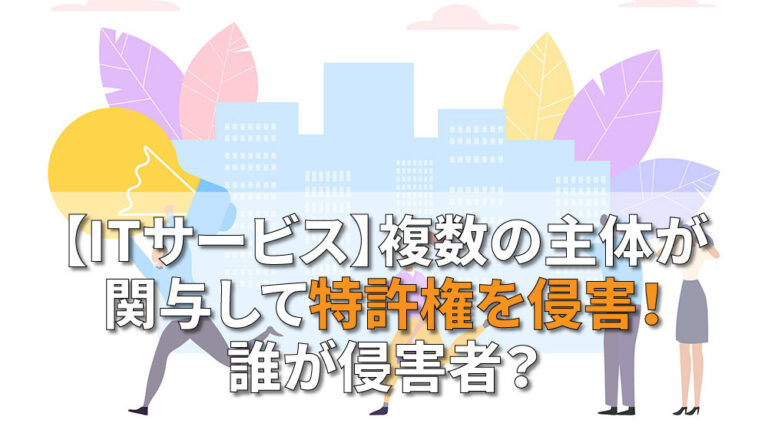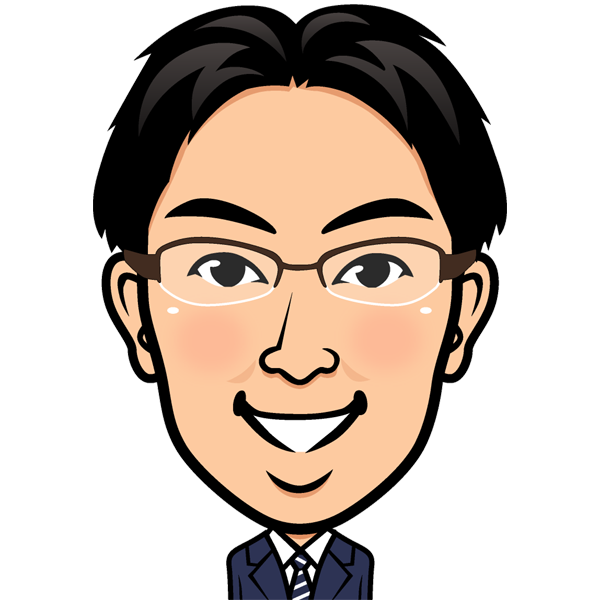
まずは、そのITサービスが、貴社の特許権に抵触しているか見極める必要がありますね!

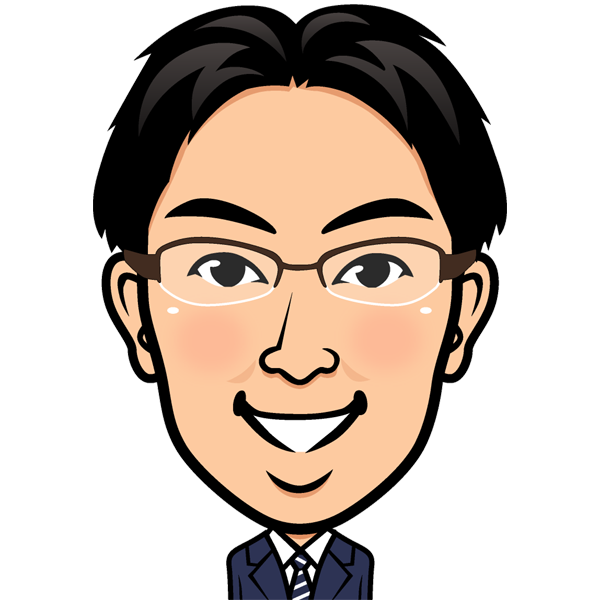
A社がそのITサービスを支配管理している場合、A社に、侵害の責任があるとされる傾向があります。
とはいえ、このあたりの見解は非常に難しいところです。ですから、今回の記事は具体例を元に、
- 複数の主体が関与する特許権侵害の背景
- インターネット関連の方法の発明について注意すべきポイント
- インターネット関連のシステムの発明について注意すべきポイント
の、3点にスポットを当ててわかりやすく解説していきましょう。
ネットビジネスで複数の主体が関与する特許権侵害の背景


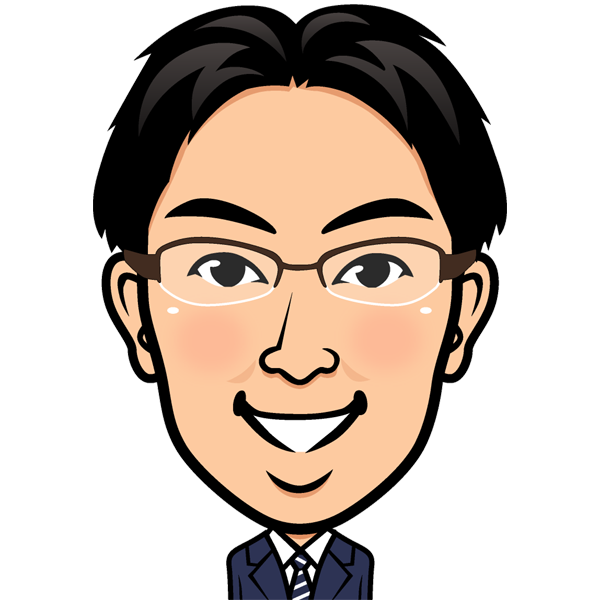
ネットビジネスにおいては、一つのサービスであっても、いろいろな会社が関与している場合が多いです。例えば、アプリ配信では次のような場合です。
- サービスを運営する会社
- プログラムを委託されている会社
- プログラムを保存しているサーバー会社
この他にもまだまだいろいろあります。いろいろな会社が絡んでいるので、「特許権を侵害している場合」においても、2社以上の複数の主体が関与していることも当然考えられます。
この場合の特許権の侵害ですが、
- 共同でサービスを提供している場合にはその両者
- 1社がサービスを支配管理している場合にはその事業者
特許権の侵害者に認定される傾向が強いと言えます。そのあたりのことを、もうすこし詳しく説明していきましょう。
インターネットの普及やネットワーク技術の進展に伴い、現在、一つのサービスやシステムであっても、複数の主体が関与している、なんて場合が多々あります。
このような状況において、サービスやシステムを特許権で保護する場合、特許発明の全ての構成要件を単一の主体が実施しているのであれば、その者に対して直接侵害の責任を追求できます。
ですから大原則として、請求項に含まれる全ての構成要件を単一の主体が実施するように請求項を記載すべきなのです。
しかし、これらの構成要件を複数の主体が分担して実施している場合には、誰に対して直接侵害や間接侵害の責任を追及することができるのかという問題が生じま す。
特に、方法とシステムの発明の場合において、複数の主体が関与する特許権侵害の問題が生じやすい傾向があります。
例えば、物の発明について使用又は販売する行為については、その使用又は販売を行った者が直接侵害の責任を負うことになります。
また、物の発明についてその物を生産する行為については、部品を組み合わせて最終的な侵害品を完成させた者が直接侵害の責任を負うことになります。
したがって、物の発明の場合、通常、複数の主体が関与する特許権侵害の問題は生じません。
これに対し、方法やシステムの発明の場合には、複数の主体が分担して方法の発明の構成要件を実施し、当該発明の全ての構成要件を実施する単一の主体が存在しない場合があります。
このような場合、いかなる状況下で誰が特許権侵害の責任を負うのかが問題となります。
また、あるシステム発明が
- 装置A
- 装置B
- ・・・
といったように複数のシステムで構成されている場合、甲が当該発明の装置Aに相当する装置を保有し、乙が当該発明の装置Bに相当する装置を保有して、 甲及び乙が各々の装置を使用する場合、当該システムを保有または使用しているのは誰なのかが問題になります。
日本の特許法には、複数の主体が分担して特許権を侵害している場合に、誰が侵害者になるかの規定はありません。
よって、大原則として、請求項に含まれる全ての構成要件を単一の事業者が実施するように、方法の発明にあっては単一の事業者が実施するであろう構成要件だけを記載し、システムの発明にあっては単一の事業者が保有するであろう構成要件だけを記載することをおすすめします。
一方、複数の主体が関与する特許権侵害の問題について裁判で争われ、特許権者が救済された裁判例があります。具体例としては次の2件の事件などです。
(知財高判平22・3・24(平20(ネ)10085号))
(知財高判平22・3・24(平 20(ネ)10085号))
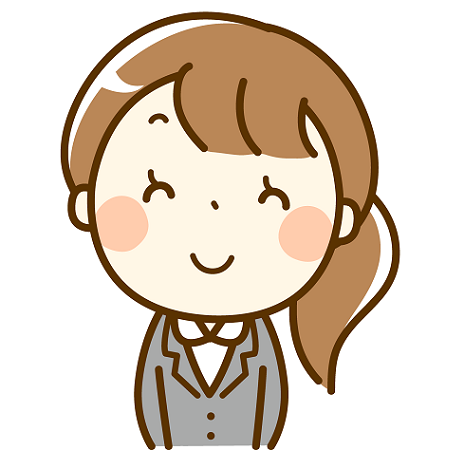
次の章では、この2つの裁判例から、インターネット関連の方法の発明、システムの発明それぞれについて注意すべきポイントについて説明していきましょう。
インターネット関連の方法の発明について注意すべきポイント
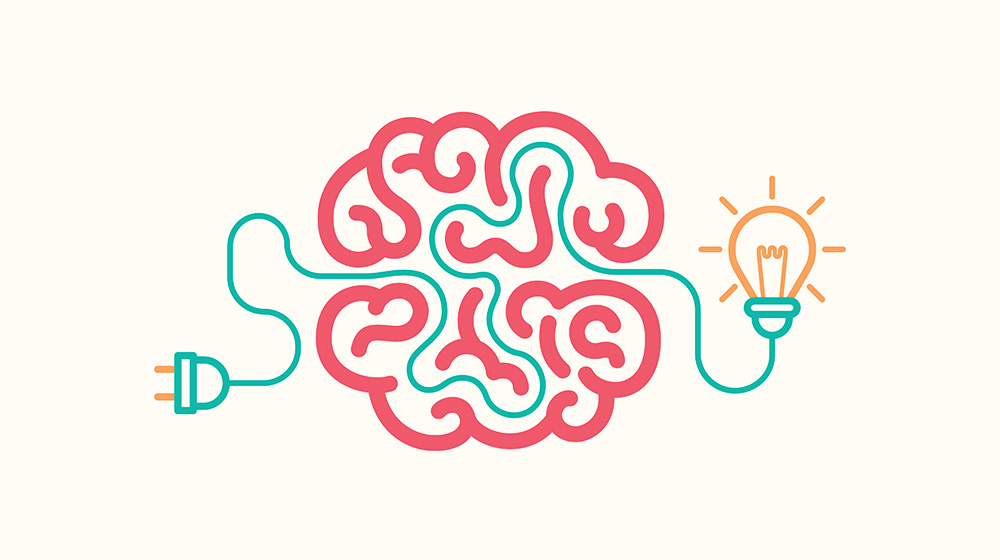

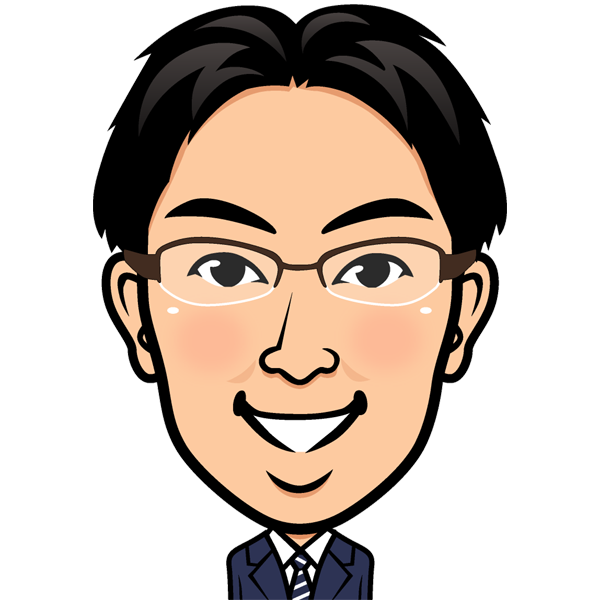
「インターネットナンバー事件」(知財高判平22・3・24(平20(ネ)10085号))では、「サーバーシステムへの情報ページに対する “アクセスを提供する方法”」というように、「アクセスを提供する方法」という形で記載していたため、クライアントによるアクセス行為を待って初めて『アクセスを提供する方法』の発明である本件発明の実施行為が完成するものではないと判断されたものと思われます。
仮にですが…
請求項に、「アクセスを提供する方法」ではなく、「アクセスする方法」と記載していた場合、ユーザによるアクセスが発明の完成には必要と判断されて、非侵害と判断された可能性があります。
一方、本件特許のように、「アクセスを提供する方法」という形で請求項を記載しておけば、仮に、その請求項の中でユーザまたはクライアントの処理を記載していたとしても、そのインターネットサービスを提供する提供主体が特許侵害者として直接侵害となる可能性があります。
つまり、
- 「アクセスを提供する方法」という形で請求項を記載した場合(=【本件特許】)
→請求項の中でユーザまたはクライアントの処理を記載していたとしても、そのインターネットサービスを提供する提供主体が特許侵害者として直接侵害となる可能性がある - 「アクセスする方法」と記載していた場合
→ユーザによるアクセスが発明の完成には必要と判断されて、非侵害と判断された可能性がある
ということです。
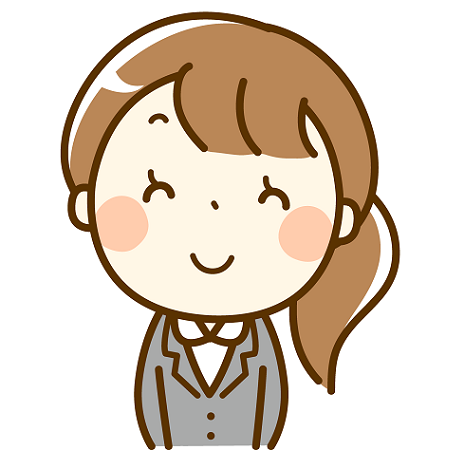
インターネット関連のシステムの発明について注意すべきポイント


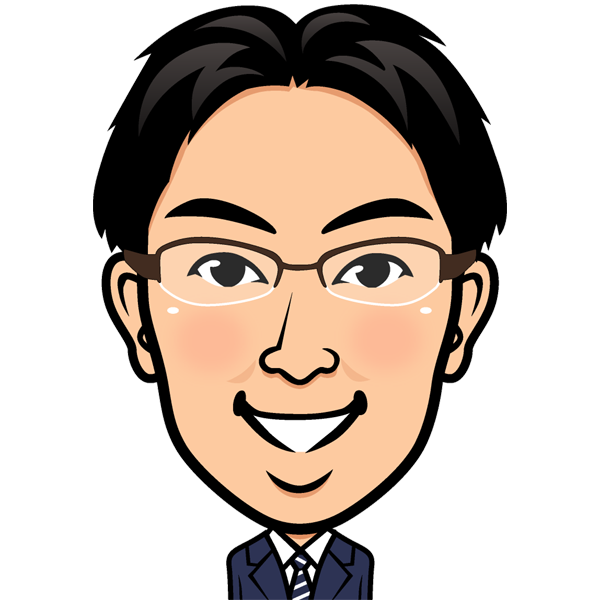
次に「眼鏡レンズ供給システム事件」(知財高判平22・3・24(平 20(ネ)10085号))について紹介します。
眼鏡レンズ供給システム事件の判決では、複数の主体が関与する特許権侵害の問題について判断する際に、
- 構成要件の充足の問題(第70条第1項)
- 発明の実施行為を行っている者は誰かという問題(第2条第3項)
を区別して判断した先駆的な裁判例です。
複数の主体が関与する場合には、発明の実施行為(特許法2条3項)を行っている者はだれかという点については、システム発明においては、当該システムを支配管理している者は誰かを判断して決定されると判断されています。
具体的に言うと、次のような場合です。
コンピュータシステムの発明であれば、通常、サービスを提供している業者が当該コンピュータシステムを支配管理しているであろうから、当該サービスを提供している業者が侵害者になるでしょう。
しかし、眼鏡レンズ供給システム事件もインターネットナンバー事件判決と同様に地裁の判決であり、その後の同様の裁判例の蓄積がないので、確立された理論ではありません。
このことに鑑みると、システムの発明にあっても単一の事業者が実施するであろう構成要件だけを記載することが推奨されます。
システムの発明を特許権利化しておけば、仮に将来、システムの発明の構成要件が複数の主体に分かれて保有されていたとしても、眼鏡レンズ供給システム事件と 同様に、当該システムを支配管理している者に対して権利を行使することができる余地が残ります。
このことから、コンピュータシステムを新たに発明した際には、システムの請求項を作ることが推奨されます。
一方、コンピュータシステムのリリース時には、
- 他の特許権者のコンピュータシステム発明に抵触しないように調査し、
- もし調査で他者の特許権の抵触することが判明した場合には、その特許に抵触しないように設計変更する
といったプロセスを付け加えることが今後重要となってくるでしょう。
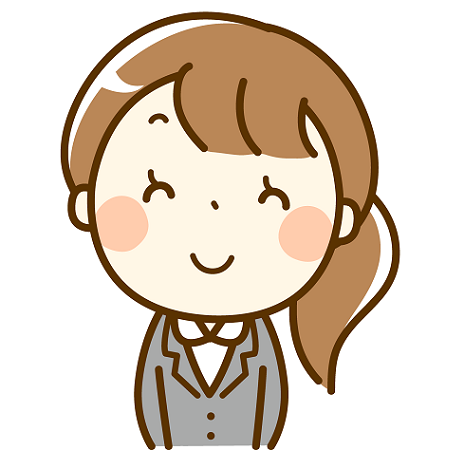
インターネットで新しいサービスを開発・リリースを考えているのであれば、特許を勉強しておくことで、
- 自分のサービスが他社の特許権に抵触することを未然に防止できる
- 自社特許に抵触する他社機能を停止させることができる
といったメリットがありますので、これを機会にしっかり勉強しておいた方がいいですね。