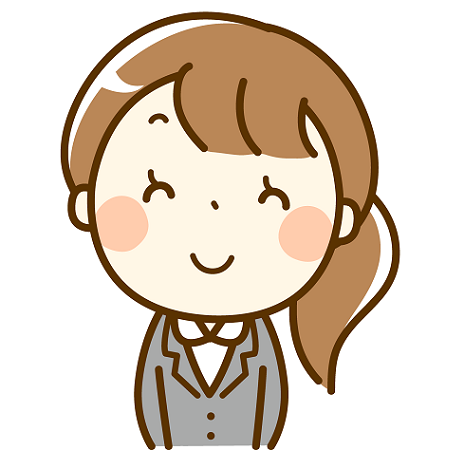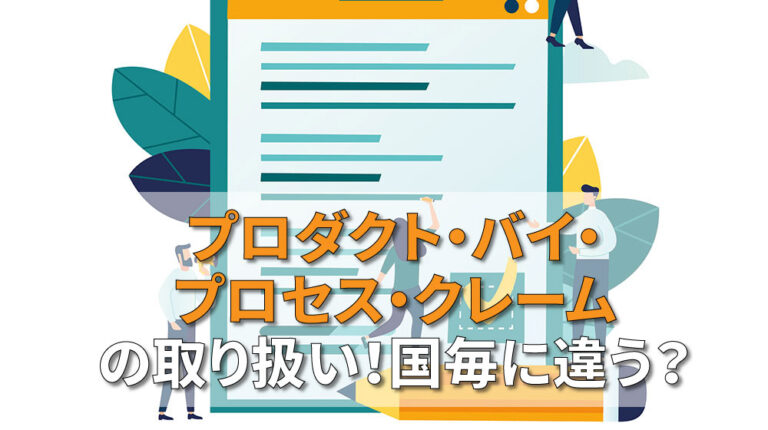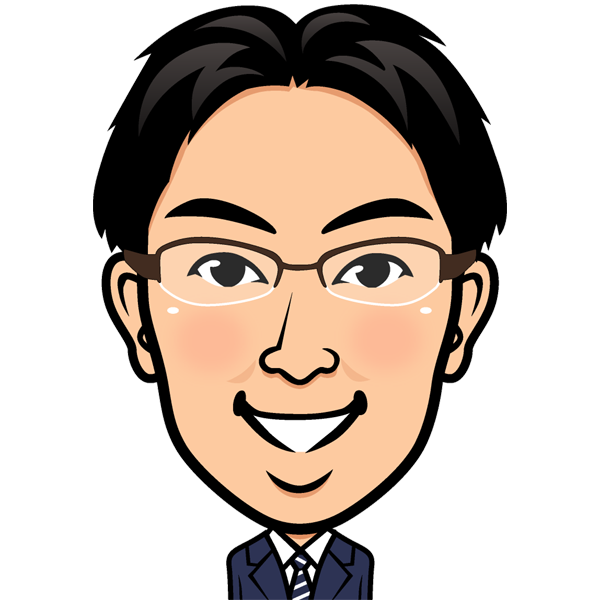
プロダクト・バイ・プロセス・クレームは特許の対象となる物を、その製造方法を記載することによってその物を特定する請求項のことです。本記事では「プロダクト・バイ・プロセス・クレーム」について詳しく解説し、日本と米国における取り扱いの違いについて説明します。
プロダクト・バイ・プロセス・クレームとは


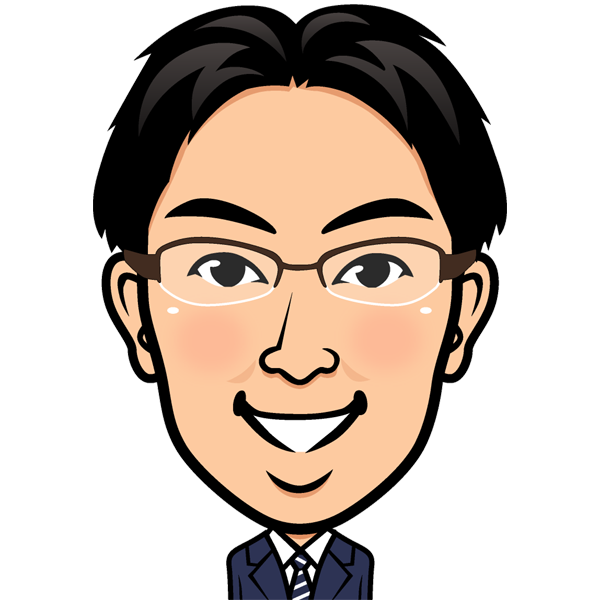
プロダクト・バイ・プロセス・クレームは「PBP クレーム」と略して呼ばれることもある請求項(クレーム)です。
製造時に新たな工程を入れたり製造時の条件や手順を変えたりすることによって新たな物質が生成されることがあります。その場合、その物質の構造が分からない場合があります。そのようなケースで、その物質の特許出願をする場合、請求項において製造方法を規定することその物質を特定することができるのです。
例えば、「・・・の方法で製造された物質A」というクレームです。
プロダクト・バイ・プロセス・クレームについては、次の3点が国毎に異なる場合があるので注意しましょう。
- その発明が明確であるか否かの判断
- 審査、審判等における権利範囲及び特許成立後の権利範囲のそれぞれの解釈
- 新規性の判断
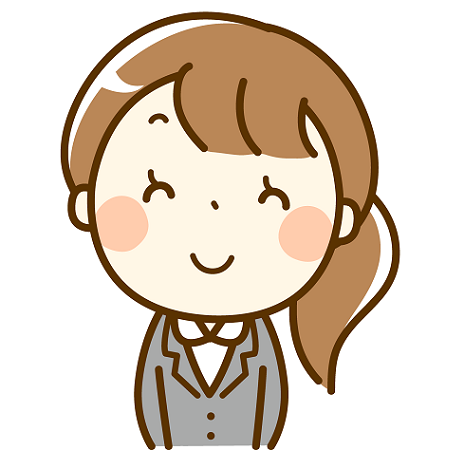
では、日本と米国ではどのように取り扱われているのか、その違いについて解説しましょう。
日本におけるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの取り扱い


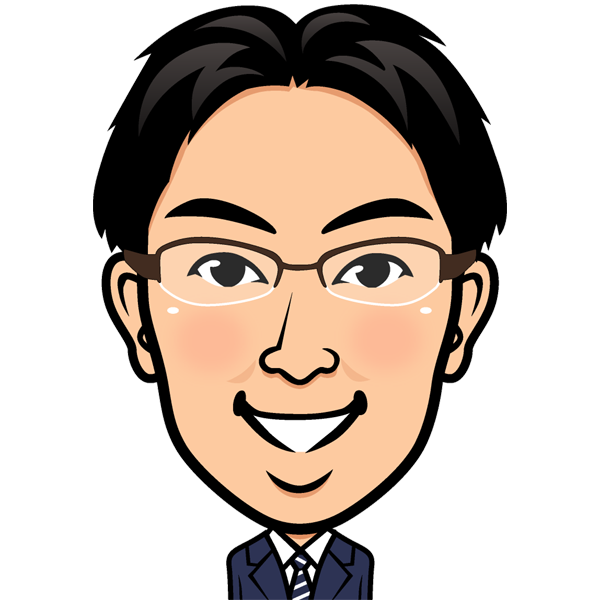
まずは日本ではプロダクト・バイ・プロセス・クレームがどのように取り扱かわれているのか、次の3点について見ていきましょう。
- 明確性
- 特許成立後の権利範囲の解釈
- 審査、審判等における新規性の判断時の解釈
明確性
まずはプロダクト・バイ・プロセス・クレームの明確性という点について、例を示しながら詳しく見ていきましょう。
日本の場合、最高裁判決(平成24 年(受)1204号、同2658号)の判示内容を踏まえた審査の概要は以下の通りです。
〇物の発明についての請求項にその物の製造方法が記載されている場合は、審査官が「不可能・非実際的事情」があると判断できるときを除き、当該物の発明は不明確であるという拒絶理由を通知します。
※ここで「不可能・非実際的事情」とは、出願時において当該物をその構造又は特性により直接特定することが不可能であるか、又はおよそ実際的でないという事情をいいます。
○出願人は、当該拒絶理由を解消するために、以下の対応をとることができます。
ア.当該請求項の削除
イ.当該請求項に係る発明を、物を生産する方法の発明とする補正
ウ.当該請求項に係る発明を、製造方法を含まない物の発明とする補正
エ.不可能・非実際的事情についての意見書等による主張・立証
オ. 当該請求項は、「その物の製造方法が記載されている場合」に該当しない旨の反論○出願人の「不可能・非実際的事情」についての主張・立証の内容に、合理的な疑問がない限り(通常、拒絶理由通知時又は拒絶査定時に、審査官が具体的な疑義を示せない限り)、審査官は、「不可能・非実際的事情」が存在するものと判断します
つまり、プロダクト・バイ・プロセス・クレームで特許権を取得するには発明が明確であることが必要です。
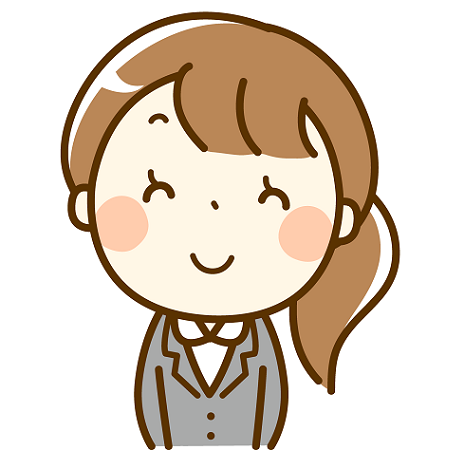
特許成立後の権利範囲の解釈
日本では、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの特許成立後の権利範囲に特徴があります。その特徴とは、プロダクト・バイ・プロセス・クレームで記載された物自体が同一であれば、製造方法によらず権利範囲に含まれるというものです。この考え方を物同一説といいます。
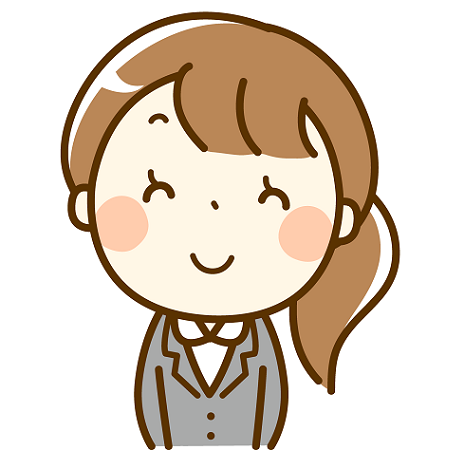
審査、審判等における新規性の判断時(発明の要旨認定時)の解釈
日本において、審査、審判等におけるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの新規性の判断は、あくまでもプロダクト・バイ・プロセス・クレームで記載された物自体が新規な物であるか否かに基づいて行われます。
つまり、特許権利化後に、プロダクト・バイ・プロセス・クレームで記載された物が記載された先行文献が見つかれば、その発明の新規性が否定され無効審判において無効になりえます。
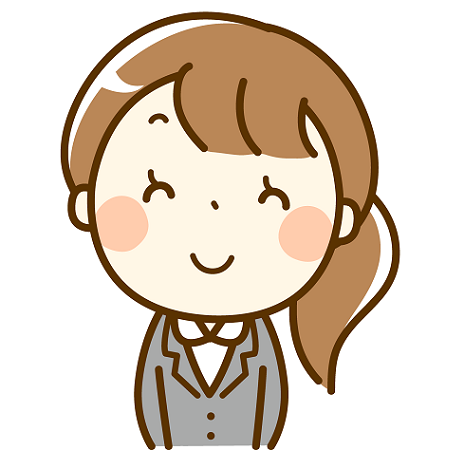
では次に、米国におけるプロダクト・バイ・プロセス・クレームについて見ていきましょう。
米国におけるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの取り扱い


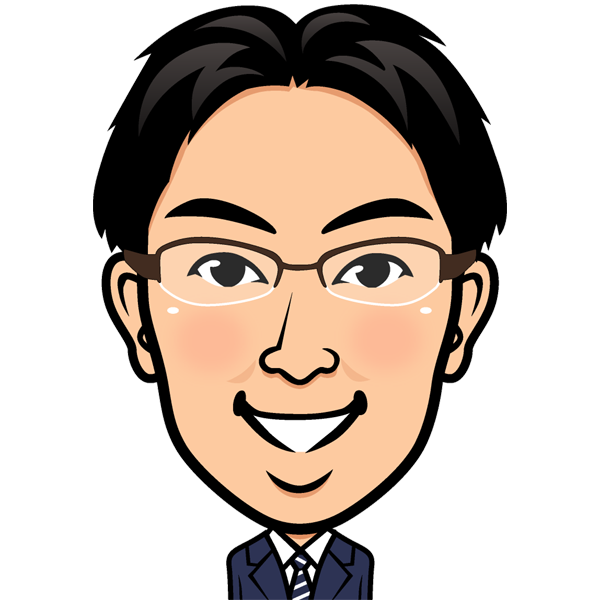
米国におけるプロダクト・バイ・プロセス・クレームについてどのように取り扱われるかを以下の3点を踏まえて解説します。
- 明確性
- 権利範囲の解釈
- 審査、審判等における新規性の判断時の解釈
明確性
日本の場合、プロダクト・バイ・プロセス・クレームは、「不可能」「非実際的事情」がある場合にのみ発明が明確と判断されます。一方、米国では、プロダクト・バイ・プロセス・クレームはそれ自体が原因で不明確になるものではないという点が異なります。
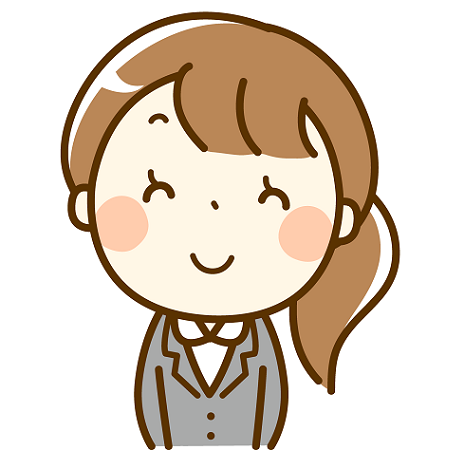
権利範囲の解釈
米国におけるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの権利範囲の解釈について、2009年の「アボット事件」を例にしながら解説していきましょう。
2009年の「アボット事件」の判決では、
プロダクト・バイ・プロセス・クレームの侵害が成立するためには、同一プロダクトがそのクレームに記載された工程を経て製造されていることが条件である
という結論が出されました。
プロダクト・バイ・プロセス・クレームは、特許成立後の権利範囲(すなわち発明の技術的範囲)を解釈する際には、請求項に記載された製法に限定されます。
この点は日本の場合と大きく異なるので、米国において、プロダクト・バイ・プロセス・クレームは積極的に使用しない方がいいでしょう。
ですから、その物質の物理的または化学構造が判明しているのであれば、以下の方法が望ましいと言えます。
- 組成物のクレームを採用する
- 物質の組成クレームとプロダクト・バイ・プロセス・クレームを併用する
また、プロダクト・バイ・プロセス・クレームではなく製造方法のクレームについても、権利紛争の交渉時に相手方に製造方法を開示させることができる可能性があります。その場合は製造方法のクレームについても有効となりえます。
また、米国では訴訟の前段階で対象の製品に関わる資料を相手方に提出させることができるディスカバリ制度があります。ディスカバリ制度によって製造方法についての資料を得られる可能性があります。
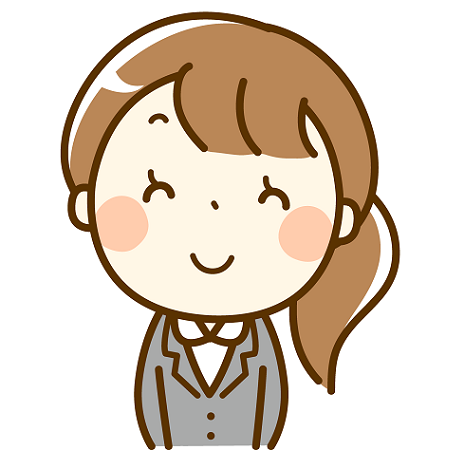
審査、審判等における新規性の判断時の解釈
米国での審査・審判等では日本と同様にあくまでもプロダクト・バイ・プロセス・クレームで記載された物自体が新規な物であるか否かで判断されます。
また、請求項に記載したプロセスを用いていない(すなわち別のプロセスで生成される)同一物が先行文献として見つかれば、その発明の新規性が否定され、無効審判において無効になりえます。この点についても日本の場合と全く同じ考えです。